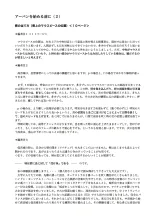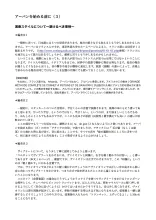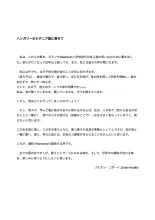New Releases
Our Staff Picks
News
Vater unser im Himmelreich
BÖHM, Georg (arr. SOKABE, Kiyonori)ゲオルグ・ベーム(arr. 曽我部清典)
Choral prelude " Vater unser im Himmelreich " by Georg Böhm for Trumpet & Pf(Organ)
ゲオルグ・ベームのオルガンのためのコラール前奏曲「天にまします我らの父よ」を、トランペットと鍵盤楽器のために編曲しました。パート譜はinCとinBbを用意しました。
Christ lag in Todesbanden
BÖHM, Georg (arr. SOKABE, Kiyonori)ゲオルグ・ベーム(arr. 曽我部清典)
Choral prelude " Christ lag in Todebanden " by Georg Böhm for Trumpet & Pf(Organ)
ゲオルグ・ベームのオルガンのためのコラール前奏曲「墓に横たわるキリスト」を、トランペットと鍵盤楽器のために編曲しました。
Christ lag in Todesbanden
BÖHM, Georg (arr. SOKABE, Kiyonori)ゲオルグ・ベーム(arr. 曽我部清典)
Choral prelude " Christ lag in Todebanden " by Georg Böhm for Trumpet & Pf(Organ)
ゲオルグ・ベームのオルガンのためのコラール前奏曲「墓に横たわるキリスト」を、トランペットと鍵盤楽器のために編曲しました。
Dinamica Impulsiva for Orchestra
YAMAMOTO, Jun山本準
The title of the piece, "Dinamica Impulsiva," translates directly into English as "impulsive dynamics," but it is a fictitious dynamics that does not exist. The title was chosen with the intention of depicting the various impulses that propel the music and create a great swell.
The original form of this piece was composed primarily between 2013 and 2015, when the composer was in his mid-fifties. This is a modified and completed version of this piece.
Music speaks for itself through its sound, so a commentary is essentially useless, but as a "guide" for listening, I will describe the composition of the piece below.
This piece is composed of several main motives, themes, fixed forms, and their developments, but it does not follow the classical sonata form, and is rather complex in its aspect.
The piece begins with the presentation of the first motive (Allegro ma non troppo) by the timpani soloist, consisting of C# and E notes. The first violin is introduced, and an important fixed note (G♭DFDA♭) is presented by the harp and celesta (Meno mosso).
Then, after a passage with a second motive characterized by dotted eighth rests and sixteenth notes, the entire ensemble begins a canon for strings (Più mosso), derived from the first motive. At the height of this canon, the first and second motives are developed, and then we enter a three-beat episode (Leggiero) with pizzicato strings, harp, and celesta. A modified melody of the second motive in the bass instruments and a third motive led by sixteenth notes appear, from which the brass chorale is derived (Risoluto assai). Next, after a recollection of the fixed form, the first motive is recapitulated and developed by the entire ensemble (Agitato).
After the slow theme of Lento is recalled, the first motive is recapitulated by the whole ensemble (Agitato), then the slow theme is played by the English horn and alto flute, which is extended by the strings, solo violin and solo cello are introduced, and the fixed motive is recalled again. After recalling the slow theme of Lento, a timpani solo based on the first motive begins and rises (Allegro ma non troppo) over a series of snare drum, and the first motive is reproduced by the whole ensemble.
After the fixed note pattern reappears (Meno mosso), an episode featuring woodwinds and percussion is inserted with the fixed note pattern as accompaniment, and the piece proceeds to the coda. The coda (Allegro ma non troppo) recalls the main motive, the slow theme, and the fixed form, and then a new theme featuring triplets is played by all instruments in unison, closing with the second note of the first motive, E, in unison.
This piece has been premiered by Tokyo Philharmonic Orchestra conducted by Hiroyuki Mito at Tokyo Opera City Concert Hall, on December 1, 2023.
曲名の“Dinamica Impulsiva”を日本語に直訳すれば「衝動的動力学」となりますが、実在しない架空の力学です。様々な衝動が音楽を推し進め、大きなうねりを生んでいく様を描き出すことを意図して題名としました。
この曲の原型は主に2013年から2015年にかけて、作曲者が五十代半ばのころに作曲されました。今回これに手を入れて完成版としたものです。
音楽は音そのもので自らを語るので、本来解説は無用ではありますが、以下聴いていただく「目安」として、曲の構成について述べておきます。
この曲はいくつかの主要な動機・主題と固定音型およびその展開から構成されていますが、古典的なソナタ形式などの構成によらず、やや複雑な様相を呈しています。
曲はティンパニ・ソロによる、C#とEの音からなる第一の動機の提示から始まります(Allegro ma non troppo)。これに、低音から順次弦楽器が絡んで次第に高揚し、第一バイオリンが導入されるとともに重要な固定音型(G♭DFDA♭)がハープとチェレスタにより提示されます(Meno mosso)。
そのあと全合奏による付点8分休符と16分音符の音型を特徴とする第二の動機によるパッセージを経て、第一の動機から派生した、弦楽器によるカノンが開始されます(Più mosso)。このカノンが高潮したところで、第一と第二の動機が展開され、次に弦楽器のピチカートとハープおよびチェレスタを中心とした三拍子のエピソードに入ります(Leggiero)。低音楽器による第二の動機の変形された旋律および16分音符に導かれる第三の動機が現れ、ここから金管楽器のコラールが導き出されます(Risoluto assai)。次に固定音型が回想された後、全合奏により第一の動機が再現して展開されます(Agitato)。
続いて、曲は緩やかになり(Lento)、イングリッシュ・ホルンとアルト・フルートによる緩徐主題の掛け合いを奏したのち、これを弦楽器が拡げていき、ソロ・ヴァイオリンとソロ・チェロが導入され、固定音型が再度回想されます。Lentoの緩徐主題を回想したのち、小太鼓の連打の上で、第一の動機を原型としたティンパニのソロが始まり高潮していき(Allegro ma non troppo)、第一の動機が全合奏により再現します。
固定音型が再び現れた後(Meno mosso)、固定音型を伴奏として、木管楽器と打楽器を中心にしたエピソードが挿入され、曲はコーダへと進みます。コーダ(Allegro ma non troppo)では、主要な動機、緩徐主題および固定音型を回想しながら進み、三連符を特徴とする新たな主題による全楽器の斉奏となり、第一の動機の二つ目の音、Eの全合奏をもって曲を閉じます。
本作品は2023年12月1日、水戸博之指揮、東京フィルハーモニー交響楽団によって、東京オペラシティコンサートホールにて、「オーケストラ・プロジェクト2023」において初演されました。
Bicinia Hungarica II for bass clef
KODÁLY, Zoltán (arr. SOKABE, Kiyonori)ゾルタン・コダーイ(arr. 曽我部清典)
2 parts music by Zoltan modally for 2 trombones.
ハンガリーの作曲家ゾルタン・コダーイが、子どもの頃の思い出を、2声の合唱曲(ビチニア)に綴った作品をトロンボーン2本に編曲しました。その第二巻です。子どもらしい題名がついているものもたくさんあり、初心者でも自然にハーモニーを感じながら、無理なく吹ける教材として作りました。もちろん、他の管楽器でも演奏できます。
Bicinia Hungarica I for bass clef
KODÁLY, Zoltán (arr. SOKABE, Kiyonori)ゾルタン・コダーイ(arr. 曽我部清典)
2 parts music by Zoltan modally for 2 trombones.
ハンガリーの作曲家ゾルタン・コダーイが、子どもの頃の思い出を、2声の合唱曲(ビチニア)に綴った作品をトロンボーン2本に編曲しました。子どもらしい題名がついているものもたくさんあり、初心者でも自然にハーモニーを感じながら、無理なく吹ける教材として作りました。もちろん、他の管楽器でも演奏できます。
40 ETÜDEN Book II by Wilhelm Wurm
WURM, Wilhelm (arr. SOKABE, Kiyonori)ヴィルヘルム・ヴルム(arr. 曽我部清典)
19世紀後半サンクトペテルブルグ管弦楽団の首席奏者として、のちにサンクトペテルブルグ音楽院教授として、ロシアのトランペット界に大きな功績を残したヴィルヘルム・ヴルムの少し易しい40の練習曲から後半の20曲をまとめました。同じヴルムの20曲のハード(難しい)練習曲の前の予習としてチャレンジしてみてください。
15 Duets by Zoltan Kodaly (Bass clef)
KODÁLY, Zoltán (arr. SOKABE, Kiyonori)ゾルタン・コダーイ(arr. 曽我部清典)
コダーイによるデュエット集低音楽器用です。ごくごく簡単なものから、少し厄介なものまで、15曲で構成されています。コダーイには、この他にたくさんのデュエットがありますが、入門編と考えて良いと思います。コダーイは「2つのパートが主従の関係ではなく、正しいイントネーションを保ちながら歌うように」と指示しています。
40 ETÜDEN Book I by Wilhelm Wurm
WURM, Wilhelm (arr. SOKABE, Kiyonori)ヴィルヘルム・ヴルム(arr. 曽我部清典)
19世紀後半サンクトペテルブルグ管弦楽団の首席奏者として、のちにサンクトペテルブルグ音楽院教授として、ロシアのトランペット界に大きな功績を残したヴィルヘルム・ヴルムの少し易しい40の練習曲から前半の20曲をまとめました。同じヴルムの20曲のハード(難しい)練習曲の前の予習としてチャレンジしてみてください。
34 ETÜDEN(18~34) for Low treble clef
BRANDT, Vassily (arr. SOKABE, Kiyonori)ワシリー・ブラント(arr. 曽我部清典)
ワシリー・ブラントの34のオーケストラ奏者のための練習曲第2巻低音用です。高音域の苦手な人のブラント入門用に完全4度下げました。低音域の足りないところは、オクターブ上げて演奏して下さい。この版で練習をして、慣れてきたらオリジナルのキーで練習するようにしましょう。
34 ETÜDEN(1~17) for Low treble clef
BRANDT, Vassily (arr. SOKABE, Kiyonori)ワシリー・ブラント(arr. 曽我部清典)
34 Etüden für Trompette(Low version) by Vassily Brandt
ワシリー・ブラントの34のオーケストラ奏者のための練習曲第1巻低音用です。高音域の苦手な人のブラント入門用に完全4度下げました。低音域の足りないところは、オクターブ上げて演奏して下さい。この版で練習をして、慣れてきたらオリジナルのキーで練習するようにしましょう。
"ENKU" for 6 female singers and 6 male singers(2021)
KAMINAGA, Sadayuki神長貞行
この《円空》は、混声合唱団 Vox humana(ヴォクスマーナ)から委嘱を受けて作曲した作品です。
仏師でもあった円空は、森に倒れた朽木などを刻み、たくさんの仏像を彫り上げました。
私が特に注目したのは三角柱の仏像です。三角柱に割った朽木を鉈のみで彫り上げて出来たものですが、素材も手法も素朴だからこその力強さが、見るものを魅了します。
ここから浮かべた発想として、三角柱風に折り曲げしつらえた方眼紙の縦の欄に歴代世界の様々なスケールを書き込み、これを素材となる「年輪」に見立て、まさにこれを縦に横に斜めに切り刻んでいく(ような)プロセスを通して、圧倒的な集中力をもってこの曲は完成しました。
初演:2021年9月28日 豊洲シビックセンターホール
コンサート名:ヴォクスマーナ第46回定期演奏会
演奏:西川竜太指揮 ヴォクスマーナ